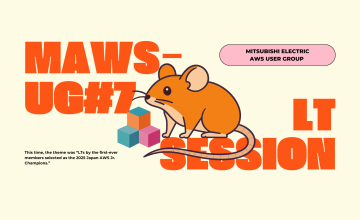取締役COOを務める小林です。10月上旬に、JEITA(電子情報技術産業協会)の仲介で、都内の大学の理工学部の非常勤講師として講義を行ってきました。JEITAがこの講座を設けている背景と目的は次の通りです。
|
<背景と目的> 近年の急速な技術革新に伴い、ITは企業活動及び国民生活の基盤として不可欠な社会インフラとなっており、我が国経済の国際競争力や国家の発展を支える源泉になっています。 |
今回、私は情報工学系の大学生・大学院生向けに「OSS✕クラウド ― 最先端の技術を取り入れ、ビジネスを俊敏に進める」というテーマでお話ししました。技術面だけでなく、ビジネス面も含めてOSSとクラウドに関わる企業の営みを紹介しました。
|
<講義概要> 先進的な仕組みが最初にOSS(オープンソースソフトウェア)として世の中に出てくる時代となった。無償で誰でも入手できるOSSだが、IT企業やユーザ企業では、単に無償を理由にOSSを採用するのではなく、ビジネス上の戦略的意図をもってOSSを扱うケースが増えている。 |
OSSについては、プログラムソースコードや情報をオープンにすると、周囲に企業や人々が集まってきて開発や利用の裾野が広がることや、企業が競争領域を強化して自社優位の市場を作り出すために非競争領域の資産を活用するビジネス思考などをお話ししました。
また、クラウドについては、ネットワークを介して提供者側と利用者側の間の対話が続き、それがサービスの継続的な進化に繋がること、またクラウドを選択するということは将来に向けた可能性や様々な余地を選択するということであり、小さく気楽に試行出来るというクラウドの特質を活かすことも含めて、それに適合するために自社のビジネス自体をアジャイルでスピード感があるものに変えることに繋がることをお話ししました。
そして、今の時代はOSSとクラウドにより最先端のITをいち早く取り入れ、それを企業の競争力に繋げる必要があることをお話ししました。
講義の最後では、OSSやクラウドに携わるオープン指向のエンジニアは常に最先端を走り続ける覚悟が必要であり、そのためには社内に籠って狭い世界で活動するのではなく、能動的に外部の情報を取りにいく行動特性を持ち、コミュニティにも積極的に関わって最先端の情報や実践的な技術・知見を取り込んでいく必要があることをお話ししました。多くの学生さんが今後、OSSやクラウドのコミュニティ活動に飛び込んでいって頂けることを期待しています。
1つ気になったのは、講義の中でAWSのアカウントを持っている方に挙手頂いたところ、僅か1割程度に留まっていたことです。大学や大学院の研究活動においては、もっとクラウドを便利に活用できるのではないかと思います。クラウド上には最先端の技術がどんどん実装されており、それらを研究活動に取り入れることが出来ます。また、コンピュータリソースの制約に囚われることが無くなり、企業の機動力を高めるのと同じように、研究活動の機動力を高めることができます。社会に出る前にクラウドを経験しておくことは、学生さんにとっても有意義なことだと思います。
我々クラウド界隈の者は、学生さんがクラウドに触り始めるキッカケを旨く作り出すなど、もっと文教領域を支援してゆく必要がありそうです。